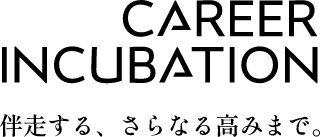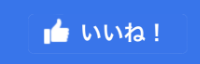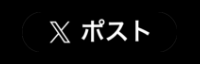はじめに

「コンサルは机上の空論である」──コンサルティング業界に身を置くと、少なからずこのような声に出会うことがあります。現場を知らない、実行性が伴わない、高額な費用に見合う成果が見えにくい──そうした批判は、コンサルタントのアウトプットが単なる提案や報告書にとどまっている場合に、特に強くなされる傾向にあります。
しかしながら、現代のコンサルティングは、単なる戦略提案にとどまらず、「クライアントと共に成果を出すこと」が本質的な価値であると再定義されつつあります。提案を超えて、現場で「やり切る」こと。すなわち"デリバリー"の重要性が、今あらためて問われているのです。
本稿では、「なぜコンサルは机上の空論と言われるのか」を考察したうえで、その認識を打破するためのデリバリーの役割と重要性について述べてまいります。
本論
1. なぜ「机上の空論」と言われるのか
コンサルティングに対する「机上の空論」という批判には、いくつかの背景があります。
第1に、コンサルタントの提案が、実行フェーズにおけるリアリティや障壁に対して十分な理解や配慮を欠いている場合です。戦略的には優れていても、現場の組織文化やリソース制約、現実的な実行力が考慮されていない場合、提案はいわゆる「絵に描いた餅」として終わってしまいます。
第2に、実行に責任を持たない立場であること。過去のコンサルティングスタイルは「提案まで」で終えるものが多く、クライアントがその後どう運用するかに関与しないケースもありました。このような「口を出すだけで手を動かさない」姿勢は、現場からの反発を招きやすく、結果として「空論」との批判に繋がってしまうのです。
第3に、成果が定量的に、かつ直接的に見えにくいことも要因と言えるでしょう。提案の質が高くても、実行フェーズで何らかの理由で失敗すれば、責任の所在が曖昧になり、「効果がなかった」「何も変わらなかった」とみなされるリスクが高くなります。また対象となる取組みによっては、検討した時期と実行するタイミングまでに長い期間を必要とし、その間の環境変化によって当初検討していた内容が使えなくなることもあります。
これらの背景が単独または複数絡み合うことにより、コンサルに対し「机上の空論」という声が上がるのは珍しいことではありませんでした。
2. デリバリーが持つ意味と役割
こうした批判を乗り越えるために必要なのが、「デリバリー」すなわち「成果を実際に実現すること」に対する責任です。もちろん依然としてクライアントが実行主体であることが主流ではありますが、コンサルタントとしてもデリバリーに責任を持つことが求められます。
デリバリーの第一の意義は、提案内容を実行に移し、クライアントと共に変化を生み出すことです。その過程では、クライアント組織の中に入り込み、実行の壁を共に乗り越え、具体的な成果につなげる姿勢が求められます。これは単なる理論の伝達ではなく、現場での伴走者としての役割です。
第二に、実行フェーズにおいて、提案の柔軟な修正と適応が必要です。実際の運用においては、想定外の課題や抵抗が生じることは避けられません。そうした際に、クライアントと共に試行錯誤し、必要に応じて戦略そのものを調整する柔軟性と責任感が、真のプロフェッショナリズムと言えます。
第三に、実行支援によって信頼が生まれるという側面があります。単なる提案者から、成果を共に出すパートナーへと変わることで、コンサルタントはクライアントからの信頼を獲得しやすくなります。これが長期的な関係性やリピート案件、レピュテーションの形成につながっていくのです。
3. コンサルに求められるデリバリー能力の深掘り
では、コンサルタントが持つべき「デリバリー能力」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。ここでは、デリバリーを担保するために必要な主なスキルや姿勢を整理します。
第1に必要なのは、「プロジェクトマネジメント能力」です。期限、リソース、関係者の調整など、多様な変数を管理しながら進捗を管理する力は、どれほど優れた提案であっても、それを形にしなければ意味がないという事実を物語っています。
第2に、「コミュニケーション能力」も極めて重要です。現場との信頼関係構築、抵抗勢力への働きかけ、上層部へのレポーティングなど、デリバリーは常に人との協働の中で進んでいきます。単に話す力ではなく、「聞く力」や「理解する力」も含まれます。
第3に、「現場理解力」も欠かせません。机上では正解でも、現場では不可能な施策は数多くあります。実務に落とし込む力、すなわちオペレーションと戦略の橋渡しをする力が、優れたコンサルタントには求められます。
さらに、変化に粘り強く対応し続ける「スタミナ」や「状況対応力」も、デリバリーの成功には不可欠です。一度でうまくいかないことを想定し、軌道修正やトラブル対応を行う際の精神的タフネスも、見落とせない要素と言えるでしょう。
そして何より重要なのは、「実行を通じて提案を進化させる」という姿勢です。
単に言われた通りに導入するのではなく、現場での試行錯誤から新たな示唆を得て、提案自体の質を高めることができる人材こそ、真に強いデリバリー力を持つと言えるのではないでしょうか。その意味で、机上の空論と揶揄されないためには、現場への深い関心、実行力に基づいた学習力、そして成果に対する責任意識の三位一体が不可欠なのです。
言うなれば、優れたデリバリーとは、紙の上に描かれた地図を片手に、ぬかるんだ未舗装の道を共に歩く旅人のような存在です。計画と現実のギャップに橋をかけるその姿勢こそが、理論を実践に変え、信頼を構築し、最終的に真の価値を生み出す鍵となるのです。
4.新たなコンサルティングのデリバリーの形
ここまでは、現在の主流である、支援主体としてのコンサルティングにおけるデリバリーの責任と、その強化のための能力に関する話でした。一方、これまでの枠組みを超えた、新たなコンサルティングのデリバリーの形も出てきています。いくつか例を挙げてみましょう。
クライアントの満足やマイルストーンベースでの報酬設
従来の固定金額での契約に加え、プロジェクトの満足度に応じて金額を上積みできる制度や、またクライアント内での一定の進捗に応じて報酬が支払われる仕組みが増えてきました。これまでは合意したSoWさえ満たせばよいものでしたが、それ以上の満足や、またクライアントの事業推進など、コンサルティング会社によってコントロールが難しいものまで含めることで、より主体的な支援を目指すものです。
成果報酬設定
これまでも概念としてはあったものの、リスクが高くなかなか普及してこなかった成果報酬型のデリバリーも増えてきています。コンサルティング会社が成果にコミットすることで、クライアントとしても費用対効果を高めることが可能となります。上の例よりも更に踏み込んだ、支援の立場から半ば実行主体となるような取組みです。
JVの設立
特にアクセンチュアなどが有名ですが、コンサルティング会社がクライアントと一緒になってJVを設立し、コンサルティング会社も一定のリスクを負うスキームです。特にデジタル領域など、クライアントが強化したい新領域においてこういった取組みが見られます。もちろん内部においては様々な役割分担がなされていますが、コンサルティング会社も実行主体として事業を推進する立場になります。
これらの取組みにおいては、もはやコンサルタントの支援を「机上の取組み」と呼ぶ人はいないでしょう。
終わりに
「コンサルは机上の空論である」という批判を乗り越えるには、理論の正しさ以上に、「成果に責任を持つ」という姿勢が必要です。実行フェーズにおける伴走と実践によって、はじめて提案が「現実に意味のあるもの」となり、コンサルタントの存在価値が問われるのです。また、そもそもデリバリーのスキーム自体も変わりつつあります。
コンサルタントが"提案屋"にとどまらず、"変革の実行者"であるためには、デリバリーの力が不可欠です。クライアントの信頼を得るためにも、また自身の専門性と誇りを保つためにも、実行の現場で汗をかくことから逃れてはならないと強く感じます。