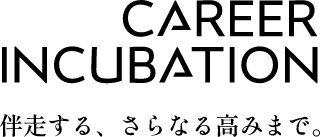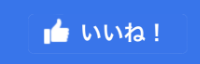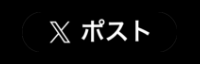はじめに

コンサルティング業界において、マネージャーへの昇格は大きな節目となります。多くの若手コンサルタントは、アソシエイトやシニアコンサルタントのようなジュニアとして経験を積んだのち、マネージャーへの昇格を目指します。しかしながら、誰もがスムーズにそのステップを乗り越えられるわけではありません。特に、年次や経験は十分のように見えても、昇格審査に通過できない人が一定数存在します。例えそれまでハイスピードに昇格してきた人であってさえ、マネージャーの昇格においては足踏みをしてしまうこともあります。ジュニアとしては評価されても、マネージャーとしては評価されない―こうしたことは何故起きるのでしょうか。
各ファームによってタイトルのつけ方が異なるように、マネージャーに求める要件やレベルは各ファームで必ずしも共通しているわけではありません。一方で、筆者が複数ファームを経験して思うのは、それでもマネージャーとジュニアに求められるスキルは違う、ということです。
本稿では、コンサルタントがマネージャー昇格でつまずく理由として多く見られる3つの欠点----「仮説構築力の不足」「プロジェクト全体設計の未熟さ」「チームマネジメントの弱さ」----に焦点を当て、具体的な事例とともにその本質を考察いたします。昇格に悩む若手コンサルタントにとって、今後のキャリア形成の指針となれば幸いです。
本論
1. 仮説構築力の不足
仮説構築力は、コンサルタントにとって最も基本かつ重要なスキルの1つです。プロジェクトの初期段階で、限られた情報をもとに核心となる論点を特定し、検証すべき仮説を立てられるかどうかが、その後の分析の質や効率を大きく左右します。
しかし、マネージャー昇格を目指す層の中でも、この仮説構築力が弱い人は少なくありません。具体的には、課題に対するアプローチが「網羅的」であっても「鋭さ」が欠けている、または顧客の関心からずれた論点を立ててしまうケースです。
もちろん仮説構築力はジュニア時代から求められるものです。但し、ジュニアに求められる仮説は、プロジェクト全体における一部分に対するものであることがほとんどです。例えば市場における特定セグメントの将来動向など、スコープを定められた中での仮説であり、比較的ナレッジベースで導き出しやすいものが多いでしょう。一方、マネージャーに求められる仮説はプロジェクト全体を通した仮説です。クライアントの課題感に対し、本当に答えるべきものは何か?クライアントはこの答えを受けとるとどういった状態になるか?このプロジェクトをやることでクライアントが得られるベネフィットは何か?-といったように、問われているものへの答えはもちろん、その背景や次のアクションまで踏まえて仮説を構築していかなければなりません。
たとえば、あるB2Bメーカーの営業戦略プロジェクトで、Aさんは用意されていた顧客リストのセグメント分析に膨大な時間をかけていましたが、顧客側の真の課題は「チャネル別販売戦略の不在」でした。目の前のワークに集中してしまい、しかも論点を外していたために、チームのリソースが分散し、期待された成果が出ませんでした。より大きな視点でクライアントの状況を観察し、本当に解くべき問いは何かを仮説として設定することがマネージャーには求められます。
2.プロジェクト全体設計の未熟さ
マネージャーに昇格するためには、プロジェクト全体の構造を設計し、ゴールから逆算してタスクを設計・管理できる能力が不可欠です。いわゆる「戦略思考」「構造化思考」が試される領域でもあります。
一方、優秀なシニアアソシエイトの中には、目の前の分析やインタビュー設計は完璧でも、「全体をどう進行させるか」「スケジュールと成果物の整合性はどうか」という視点が弱い人がいます。これは、「優秀なプレーヤー」であることと「優秀なマネージャー」であることの間にある、大きなギャップの1つです。
マネージャーに求められるのは、そうした優秀なプレーヤーの作成した成果物を束ねてプロジェクト全体のゴールに近づけていく設計力です。タスクを並べるだけではなく、それらの依存・相互関係を見ながら、まさに「全体」を設計していく必要があります。
実際に、あるプロジェクトでBさんは、クライアントに好評な分析パートを作成したものの、他のワークストリームとの整合性が取れず、全体会議で方向性がバラバラになるという事態を引き起こしました。チームを導く存在として、全体構造を俯瞰できるかどうかが、昇格審査では重視されます。
3. チームマネジメントの弱さ
マネージャーに昇格するということは、個人としての成果だけでなく、チームとして成果を出す責任を持つことを意味します。後輩への業務配分、育成、フィードバック、さらにはクライアント対応とのバランスなど、マルチタスクな役割が求められます。
しかし、チームマネジメントの経験が乏しい人は、ここでつまずくことが多いです。たとえばCさんは、ロジカルな分析では定評がありましたが、後輩に仕事を任せることが苦手で、結局すべてを自分で抱え込んでしまい、プロジェクト終盤には疲弊してパフォーマンスが落ちてしまいました。
またDさんは自身があるストリームを実務担当し、別のストリームをジュニアメンバーに任せていましたが、自分の担当部分のボリュームが大きく、多くの時間を割いてしまいました。結果としてDさんによるジュニアのレビューが遅れたため、そこがボトルネックとなり、プロジェクト全体のスケジュールに遅延が発生してしまいました。
マネージャーは自身のタスクだけでなく、メンバーのタスクに対しても目を配る必要があります。全体をうまくコントロールするためには、プロジェクト全体設計に加え、そうした日々のマネジメント・オペレーションにも気を配らなければなりません。
マネージャーに求められるのは、「自分がやった方が早い」ではなく、「いかにチームとしてパフォーマンスを最大化するか」の視点です。時にはメンバーの成長に時間を使うことも必要であり、そのバランス感覚が問われます。
終わりに
【実践のためのヒント】
- 過去プロジェクトの成功・失敗要因を言語化し、自分の仮説力と構造力を棚卸ししましょう。
- 月1回、他チームのマネージャーや上司と模擬プロジェクト設計を行い、他者視点の設計力を学びましょう。
- チームメンバーとの1on1を定例化し、フィードバックスキルと育成意識を鍛える時間を確保しましょう。
これらの取り組みは、マネージャー昇格に必要な3つのスキルを段階的かつ継続的に伸ばす土台となります。
マネージャーへの昇格は、単に年次や勤続年数によって達成されるものではありません。むしろ、「仮説構築力」「プロジェクト全体設計」「チームマネジメント」という3つのスキルが一定水準を超えているかどうかが、最も重要な評価ポイントとなります。
本稿で紹介したような事例に見られる通り、「優秀な実行者」から「優秀なリーダー」へのシフトには、意識とスキルの両面でのアップデートが不可欠です。自分自身の強みと課題を正しく見極め、昇格に向けて戦略的に成長機会を設計することが、これからのコンサルタントに求められる姿勢ではないでしょうか。
...とここまで書いてしまうと、中にはマネージャーへの昇格をしり込みする人も出てくるかもしれません。その気持ちは理解できますが、筆者個人としてはマネージャーになることがコンサルタントとしての1つのマイルストーンになるとも考えています。なることへのハードルは高い一方、得られる自由度も高くなります。
プロジェクト全体の仮説をリードし、設計し、チームをまとめてクライアントへ価値が提供できる-自身のコンサルタントとしての価値を実感できるポジションであることは間違いありません。是非このハードルを乗り越えてみてください。