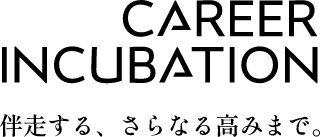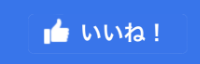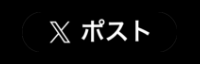プロ経営者インタビュー 杉山 大祐 氏 株式会社ツバキスタイル / 椿化工株式会社 / 株式会社BEAUTYCLE 代表取締役社長 (2025.10)

プラスチック容器業界において、従来の「作って捨てる」モデルから「循環型」への転換を図る革新的な取り組みを推進しているツバキスタイル。代表取締役社長の杉山大祐氏は、ユニ・チャーム、アディダス等でのマーケティング経験を経て、ツバキスタイルではプロ経営者として変革を主導してきた。同社は業界初となる完全循環型ビジネスモデルの構築に挑戦しており、4年で売上1.5倍の成長も達成。5社にわたるキャリアで培った経営哲学、業界のパイオニアとしての使命など、杉山氏に20の質問に答えていただいた。
プロフィール
- 杉山 大祐 氏
株式会社ツバキスタイル / 椿化工株式会社 / 株式会社BEAUTYCLE 代表取締役社長
https://tsubakistyle.co.jp/ -
1996年ユニ・チャーム株式会社入社。営業を経験後、マーケティング本部でブランドマネージャーを務める。2007年アディダスジャパン株式会社に転職し、マーケティング事業本部でディレクター職などを歴任。2018年岡本株式会社にて執行役員として商品本部副本部長、マーケティング統括部長を務めた後、2020年オレンジセオリージャパン株式会社代表取締役社長に就任。コロナ禍での事業立て直しを経験した後、2021年10月より現職。プラスチック容器業界において完全循環型ビジネスモデルの構築を推進し、業界のパイオニアとして環境問題の解決に取り組んでいる。
インタビュー
[1]自己紹介をお願いします

大学卒業後、ユニ・チャームという消費財メーカーに就職し、5年間営業、その後6年半ほどマーケティング部門で過ごしました。当時のユニ・チャームは、P&Gや花王と競合し、マーケティングの分野で有名になり始めた頃で、私はブランドマネージャーをしながらビジネスの基礎を学びました。
その後、もともとスポーツ業界に興味があったため、アディダスジャパンに転職しました。アパレルのMDからキャリアをスタートさせ、12年ほどマーケティング部門で過ごし、最終的には事業部長を務めました。
40代半ばでキャリアをさらに進めたいと考え、国内最大手の靴下メーカー、岡本で執行役員として商品部やマーケティング部の責任者を務めました。その後、アディダス時代の人脈経由で、アメリカのフィットネスクラブ「オレンジセオリー」の社長ポジションの話をいただき、初めて社長として経営に携わることになりました。
着任早々コロナ禍に入り、固定費ビジネスであるフィットネスジム経営において大変な苦労を経験しました。1年半ほどかけて黒字が見え始めた頃に、投資ファンド経由で現在のツバキスタイルの話をいただき、今に至ります。
[2]現在のご自身の役割について教えてください
投資ファンドがM&Aによって買収したプラスチック容器メーカー、ツバキスタイルの代表を務めています。前オーナーは一代で年間約50億円の売上を築き上げた方でしたが、後継者がいないことを理由に全株式をファンドへ売却されました。
この会社に来て気づいたことは、それまではオーナーが意思決定を一手に担い、組織が受け身の構造になってしまっていることでした。事業をさらに拡大していくためには「オーナー依存型」から「組織経営」へと転換する必要があったのです。
私の最初のミッションは、組織の基盤を再構築することでした。部門長や役員クラスの人材を育成し、権限を委譲していく。このプロセスには多大な時間と労力を要しましたが、組織に自律性を持たせることで、持続的な成長の基盤を築くことができました。
もう一つの大きな課題は事業の方向性です。世界的なSDGsの潮流の中で、従来型のプラスチック製造業が時代に逆行する存在になりつつあることでした。そこで目指したのが、根本から環境対応を考える"フル循環型ビジネス"のパイオニアになることです。
不要になった容器を回収し、再資源化した上で、再びボトルとしてよみがえらせる「Bottle to Bottle」の仕組みを、飲料業界以外で初めてとなる、化粧品やトイレタリー商品の分野で実現しました。技術的な困難は多々ありましたが、結果的に4年で売上を1.5倍に成長させることができています。
[3]小中学生時代はどんなお子さんだったのでしょう?
私の父は小さな貿易会社を経営していましたが、大きな借金を何回か背負うような厳しい状況もありました。それでも、動揺せずに目の前のことをコツコツやり続ける父の姿を見て育ったため、楽天的で切り替えの早い性格になったと思っています。
また、誰もやらないなら自分がやるしかないという感覚で、小学校の時から学級委員長などのまとめ役をよく引き受けていました。特にリーダーになりたいという意識はありませんでしたが、自然とそういう役割を担うことが多かったですね。
[4]高校、大学時代はいかがですか?リーダーシップの芽生えのようなものはあったのでしょうか?
 高校に進学してからラグビーを始めたのですが、ここで初めてキャプテンを経験しました。この時も手を挙げてキャプテンになったわけではありませんでしたが、個性的なメンバーの集まりでまとまりがなく、誰もまとめようとしなかったので仕方なく引き受けた感じです。
高校に進学してからラグビーを始めたのですが、ここで初めてキャプテンを経験しました。この時も手を挙げてキャプテンになったわけではありませんでしたが、個性的なメンバーの集まりでまとまりがなく、誰もまとめようとしなかったので仕方なく引き受けた感じです。
特に足が速いわけでもなく、パスやキックのスキルが上手なわけでもない、要する私自身は凡人だったわけですが、周りには高いスキルを持った才能あふれた選手がたくさんいて、そういった選手達をどう活かすのかがキャプテンの私に託された役目でした。ラグビーはポジションごとに役割が明確に分かれており、求められる能力も異なります。
これは会社経営と非常に似ていて、経理が得意な人、営業が得意な人など、それぞれの強みを適材適所に配置して組織として回していくという点で共通しています。当時は面倒だと感じることもありましたが、今振り返ると、現在の自分のマネジメントスタイルに学生時代の経験が影響していると感じます。
[5]ご家族やご親戚に経営者はいらっしゃいますか?
前述の通り、父が貿易の会社を経営していました。小さな会社でしたので、何かあったら全て自分でリスクを背負わなければならない、何があっても言い訳はできないという姿勢を間近で見て、自責と自走の概念を学びました。
[6]ご自身の性格について教えてください
楽天家だと思います。悪い結果を長く分析するよりも、なぜ成功したのかということを考える方が多いですね。もちろん反省もしますが、成功の理由を考える方が面白いし、実は難しいんです。
また、理屈で考えるよりもインスピレーションで動くことが多いです。「これは今やらなければ」と直感的に思った時は、すぐに行動に移してしまいます。
[7]いつ「経営者になろう」と思われましたか?
もともとは父への尊敬から「経営者」という存在に漠然と憧れを抱いていましたが、具体的に意識するようになったのはアディダスにいた頃にきっかけがあります。ある海外フィットネス企業との協業プロジェクトを進めていた中で、偶然その日本法人社長の募集があることを知り、思わず手を挙げたわけです。「自分がトップとして関わらなければ、この事業をさらに飛躍させることはできない」と、強い使命感を抱いたからです。
しかし、当然ながら採用される事はありませんでした。役員経験もない自分が社長に選ばれるはずもなく、その時に「経営者になるには、相応の経験やプロセスを着実に踏まなければならない」という現実を痛感しました。そして、そのときの使命感と悔しさは私の原動力となり、経営者になるための具体的なステップを真剣に考えるようになりました。振り返れば、この経験こそが私が経営者を志すきっかけになったと思います。
[8]経営者に必要なメンタリティ、スキル、経験とは何でしょう?
まずは、プロ経営者として会社の経営を委任される際に、ビジョンに対する使命感を直感的に感じること。そして、経営課題と自分の強みがフィットするかどうかを、限られた情報と時間で判断する能力が必要です。プロ経営者は、なぜ自分が呼ばれたのかを第一に把握しなければなりません。あと、私のように投資ファンドと二人三脚をする場合は、事業会社とはまた違う強いメンタリティが必要です。限られた時間で彼らに事業のありさまを正しく伝え、チャンスがある事を明確に伝えなければなりません。
そして、何かに依存せずに生き抜くハングリー精神も重要です。大手企業であれば定年まで安定した生活ができるかもしれませんが、プロ経営者は自分の結果にコミットし続ける覚悟がなければなりません。
[9]他に経営者に必要な資質や能力などありますか?
第一に、真摯さと素直さです。人の話にしっかり耳を傾けることができなければ、組織の能力を高めることはできないと思います。
第二に、人の役に立ちたい、社会に貢献したいというマインドです。自分の地位や名声ではなく、人の喜びや社会への貢献をモチベーションにできることが重要です。
最後に、常に自責であることです。思い通りにいかない時は必ず原因があり、その原因は最終的に自分にあることを受け入れられるかどうかです。他責にしてしまうと、そこで思考が止まってしまいます。
[10]これらのスキルなどをどこで手に入れたのでしょうか?
真摯さや自責の考え方は、新卒で入ったユニ・チャームで創業者の高原慶一朗氏から学びました。「会う人、皆師匠」「原因自分論」「変化価値論」という言葉を教わり、これが経営に必要なエッセンスの基礎となりました。
ハングリー精神は、アディダス時代により強く意識するようになりました。外資系企業では皆がキャリアアップを目指してギラギラしており、短期間で成果を出さなければ取り残される環境でした。この経験が、依存せずに自立して結果にコミットする姿勢を身につけるきっかけになりました。
[11]業界のプロとしての知見はいかがでしょう?やはり必要だとお考えですか?
あるに越したことはありませんが、経営課題と自分の強みが合致すれば、経営者として十分やっていけると思います。私はこれまで2つの社長職を務めていますが、どちらも業界のプロとしての経験はありません。フィットネス業界もスポーツ業界とは異なりますし、現在のプラスチック容器製造業も全く新しい分野でした。
ただし、業界にはそれぞれ押さえておくべき「ツボ」があります。私はこの会社におけるそれは現場を知ることだと考え、新社長として取引先への挨拶回りより前に、工場の現場に入り込むことを決めました。朝から夕方まで全工程で自分も作業を行い、現場の人たちと話をしながら3か月間過ごしたのです。
もちろん作業内容を習得することではなく、現場がどう動いているか、人が何をモチベーションに働いているか、利益を上げるトリガーが何なのかを肌で感じることが目的です。現場を知ることは業界を知ることにつながると考えています。
[12]過去に体験した最大の試練やストレッチされたご経験について教えてください
私にとって最大の試練は、オレンジセオリージャパンの社長として経験したコロナ禍です。
就任からわずか2ヶ月で全国の店舗が休業となり、収入がほぼゼロになる中で固定費だけが積み上がりました。急成長していた会社が一転して赤字転落の危機に陥り、経営者として毎月悪化する損益と向き合いながら、事業の存続可能性を判断しなければなりませんでした。1年半ほどかけてようやく黒字が見え始めたのですが、この経験から、経営者の願望と現実的な方向性を切り分け、迅速に意思決定することの重要性を学びました。
現職においても、強烈なワンマン経営からの組織化という課題がありました。人事制度も評価制度もない状態から、根本的な組織改革を2~3年かけて実行しました。まさにゼロから会社を作り直すような感覚でしたが、自分にとって大きな学びの機会だったと捉えています。
[13]経営者を志す者には、どのような努力や学びが必要でしょうか?
苦労は買ってでもしろという言葉がありますが、実際は誰も苦労したいとは思いません。しかし、何か困難に直面した時に「これは自分にとって学びの機会だ」「この先に良いことがある」と考える姿勢が経営者には必要だと思います。
また、私は5社で働いてきたことで、強制的に新しいことを学ばなければならない状況が何年かおきに訪れています。
年を重ねても新しいことに挑戦し続けることが重要で、自らそういう状況を作り出さなければ人は成長しないと考えています。マンネリになった時に「新しいことをして自分を刺激しなければ」と思える感覚を持つことが、新しい価値を生み出すために必要だと思います。
[14]今までに影響を受けた先輩や師匠といえるかたはいらっしゃいますか?
3人います。
1人目は、ユニ・チャームで新入社員時代の営業支店長だった方です。父親が倒れた時に会社を辞めて家業を継ぐと申し出た私に対し、「会社を辞めるのはいつでもできる。今すぐ帰っても君ができることは限られている。もう少し様子を見てからにしないか」と引き止めてくれました。もしその時に辞めていたら今の自分はなかったでしょう。
2人目も同じくユニ・チャームで当時最年少の常務取締役になった方です。この方も私が会社を辞めようとした時に引き留めてくれ、その後やりたいと思っていたマーケティング部門に引っ張ってくれました。その20年後、岡本で執行役員の経験をするきっかけをくれたのもこの方でした。経営者になる入り口を作ってくれた人です。
3人目は、ラグビー日本代表のヘッドコーチを務めるエディー・ジョーンズ氏です。アディダス時代から個人的にお付き合いがあります。彼からは数えきれないほどの学びを得ましたが、最も強く感じているのは「誰よりもハードワーカーであること」です。彼は24時間、常に頭の片隅で仕事を考えています。これは従業員に強いることではなく、自然とそうなってしまう生き方です。まるで子育てと同じで、「今日は日曜だから子育てはしない」とは言えないのと同じです。会社を家族のように捉えれば、自然と仕事のことが頭から離れない。その姿勢から、経営者としての覚悟や在り方を学び続けています。
[15]キャリアの成功とは「計画的に努力して成し遂げるもの」でしょうか?それとも、「偶然や人との出会いなど、運が影響するもの」だとお思いですか?
運や偶然はもちろんあると思いますが、それは後になって振り返ってストーリーを美化するためのおまけのようなものです。もちろんですが、私はそれを当てにして仕事をすることはありませんし、成功にはそれが必要条件だとも思っていません。ハードワークしてしっかりした準備をすることで、失敗しても後で身になります。本当の実力、本質的な力はそういうところに宿ると信じています。
[16]なぜ起業ではなかったのでしょうか?
私は起業を避けているわけではなく、起業しないとできないことがあれば起業しようと考えています。ただ、今はまだプロ経営者として経験を積んだ方が良いと思っているのです。
[17]特別な信条やモットー、哲学などをお持ちですか?
「己を知る」「身の丈を知る」ということです。これは経営者になればなるほど必要なことです。自分がどこまでできるか、どういうことができるかを知っていないと、経営者は務まらないと思います。
そして身の丈以上のことをしたいと思ったら、足りないピースを見つければよいのです。時間が限られたプロ経営者は、自分の今の時点での身の丈を知って、足りないピースをその瞬間に集めないと、限られた期間で成果を出すことはできません。自分の成長を期待している時間はないですし、成長は保証されるものでもありませんから。
[18]経営者となった今、何を成し遂げたいとお考えでしょうか?
業界のパイオニアになることです。自社の発展だけでなく、プラスチック業界に完全循環型の環境対応ビジネスプラットフォームを作ることです。同業他社、行政、学術機関も全部巻き込んで、業界全体に大きなうねりを起こしたいと考えています。
企業の価値は最終的には社会貢献です。社会貢献して従業員を幸せにすること。これに取り組んでいく使命感を、日増しに強く感じています。
[19]現在のポジションを去る時、どういう経営者として記憶されたいですか?
私がどう記憶されたいかというより、私の在任期間に会社が成長し、社員ひとりひとりが「自分がこれを成し遂げたんだ」と心から感じてもらえればそれ以上望むことはありません。「私たちは大きなことを成し遂げた」「業界を変える一端を担った」と、誇りを持って振り返ってほしいのです。当たり前ですが、会社の成長は、社員全員の努力の積み重ねによって生まれるものです。
無論、私自身が「業界を変えた経営者」と評価されたい、記憶に残したい、という願望はなく、むしろ、私がいた時に、社員が自分自身の成長を実感してくれること―それこそが、経営者として最も大切にしたい記憶の残し方だと思っています。
[20]20代、30代のビジネスパーソンにメッセージをお願いします
 若い頃から経験を積み、ポジションを上げれば携われる仕事のスケールは大きくなります。ただ、何を成し遂げたいか、何を変えたいかを徹底的に考えることが重要です。そしてそれが「経営者でしかできないことなのか」を自問してください。
若い頃から経験を積み、ポジションを上げれば携われる仕事のスケールは大きくなります。ただ、何を成し遂げたいか、何を変えたいかを徹底的に考えることが重要です。そしてそれが「経営者でしかできないことなのか」を自問してください。
明確なビジョンを描き、それが自分でなければできないのかを常に自問自答する。自分でなければできない、自分がやりたいと思えることであれば、経営者としてそれに挑戦すれば良いと思います。
Free
Consultation
10年以上の経験を持つ
専任の転職パートナーが
あなたの転職活動に伴走します。 あなたのキャリアに関する相談相手として、
これまでのご経験や今後のポテンシャル、
将来の展望を整理し、よりふさわしいキャリアをご提案します。
転職支援で受けられること
- 専任パートナーとの個別相談
- 履歴書・職務経歴書の作成・添削
- 年収や待遇の交渉代行
- 非公開求人の紹介
- キャリアプランの作成支援
- 効果的な自己PRや実績のアピール方法指導
- 業界内でのコネクション作り支援
- 業界別の最新動向やトレンド情報
- 現職の課題分析と将来のキャリア設計
- 業界特化型のスキル研修
- 入社後のフォローアップ体制