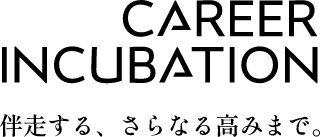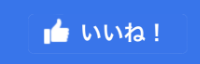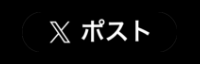事業承継後の中小企業で進む「組織づくり」と新しい人材の役割 ~マーケティング・商品開発・経営企画をゼロから立ち上げる面白さ~ (2025.07.29)
キャリアインキュベーションの村木です。日本の消費財、食品、外食、小売業界では、ここ数年で事業承継やM&Aによる経営交代が急速に進んでいます。後継者不足や市場環境の変化を背景に、創業家がバトンを外部のプロ経営者に渡し、企業を次の成長フェーズに導こうとするケースが増えています。PEファンド投資先の企業だけでなく、事業会社においても、創業者が「自分の代で終わらせたくない」と考え、外部の専門人材に未来を託す動きが目立ってきました。
このような企業に共通するのは、商品やブランドのポテンシャルはあるのに、組織としての基盤や仕組みが整っていないという点です。特に、人事、マーケティング、商品開発、経営企画といった機能が未整備なことが多く、ゼロから仕組みを作り上げていく余白が大きいのです。今回は、こうした事業承継フェーズの企業で進む「組織づくり」と、そこで求められる新しい人材の役割について考えてみます。創業者依存からの脱却が、次の成長の条件
多くの中小企業では、長年にわたり創業者の強いリーダーシップ、カリスマ性や天才的な商品開発力によって成長してきました。特に食品や消費財の分野では、創業者の"勘"や"経験"によってヒット商品が生み出されるケースも珍しくありません。例えば、ある地方の食品メーカーは、創業者の発想から生まれた独自の加工食品がヒットし、地域ブランドとして成長しました。しかし、こうした属人的な経営スタイルは、事業承継後には限界を迎えることがあります。
外部からプロ経営者を招くと、まず着手するのは「仕組みづくり」です。商品開発や販売、採用、評価制度といった領域を、創業者の個人技から脱却し、組織として再現性のある形に整えていくことが求められます。特に、BtoC企業としてブランド力を高め、消費者との接点を拡大していくためには、マーケティングや商品開発、経営企画といった機能を体系的に立ち上げることが不可欠です。事業承継フェーズで立ち上がる4つの機能と役割
1. 人事:採用と組織文化を再定義する
承継後の企業において、人事は最も重要なファーストステップです。優秀な人材を採用できる仕組みがなければ、組織は強くなりません。特に商品開発やマーケティングの経験者、デジタル人材など、これまでの企業にいなかったタイプの人材を採用する必要があるため、採用そのものを"マーケティング視点"で考えることが求められます。
例えば、ある外食チェーンでは、承継後に採用広報を強化。社員インタビューやSNSでの情報発信を通じて、働く魅力を打ち出すことで応募者数が大幅に増加しました。また、別の飲料メーカーでは、従業員紹介制度を導入し、現場からの推薦で優秀な人材を採用する仕組みを作ったことで、早期離職率が低下しました。
さらに、評価制度や等級制度が存在しない企業も多く、制度設計をゼロから作り上げるやりがいもあります。「創業者の目利きで昇格が決まる」といった属人的な評価を、再現性のある仕組みに置き換えることは、組織成長にとって非常に重要です。2. マーケティング:ブランド再構築と顧客接点の強化
承継後の企業にとって、マーケティングの役割は極めて大きいです。これまで口コミや既存顧客に依存していた企業が、新規顧客を獲得し、ブランド価値を高めるためには、マーケティング戦略の立ち上げが欠かせません。
特にBtoC業界では、SNSやECサイトの運用、キャンペーン施策などを通じて、ブランドの「世界観」を消費者に伝える必要があります。マーケティング担当者は、商品開発部門と連携しながら、「誰に、どんな価値を届けるのか」というコンセプト設計から関わることになります。
実際に、ある老舗菓子メーカーでは、承継後にブランドサイトやSNSを刷新し、若年層向けの商品訴求を強化したことで売上がV字回復しました。また、別の外食企業では、マーケティング部門が中心となり、ターゲット層を明確に設定した新メニューを開発。SNSでの発信と店舗体験を組み合わせることで、若年層の新規顧客獲得に成功しました。3. 商品開発:創業者依存からの脱却と新しい仕組みづくり
消費財や食品業界では、商品開発は企業の命綱です。承継後の課題のひとつが、創業者の天才的な発想力や嗅覚に依存していた商品開発を、組織的なプロセスに変えていくことです。
新しい経営陣のもとで、
●消費者調査や購買データを活用した企画立案
●商品コンセプトの設計とテストマーケティング
●ブランドポートフォリオの再構築
4. 経営企画:戦略を形にし、現場と経営をつなぐ
経営企画は、経営者の構想を戦略に落とし込み、現場が動ける形にしていく役割です。特に承継フェーズでは、
●中期経営計画や数値目標の策定
●KPIや評価指標の整備
●経営会議の運営や意思決定の仕組み化
といった業務が求められます。ある外食企業では、承継後に経営企画部を新設し、出店戦略と財務計画を一体で設計したことで、無理のない成長が実現しました。別の消費財メーカーでも、経営企画部が主導して在庫管理と販売予測の精度を高めたことで、収益性が大きく改善しています。
承継後にプロ経営者が改革を成功させた実例
ある地域発の食品メーカーでは、創業者からプロ経営者への交代後、まず半年間で評価制度と商品開発プロセスの再設計に着手しました。新社長は、現場社員との面談を重ね、既存ブランドの強みと弱みを整理。1年後には新しいPB商品がヒットし、売上が20%以上増加。マーケティングチームを新設し、SNSでの発信を強化したことで、これまで接点のなかった若年層の顧客獲得にも成功しました。さらにその後は、海外展開やECチャネル強化にも取り組み、ブランドを全国区へと押し上げるまでに成長しました。
承継後企業で得られるスキルとキャリアの広がり
承継フェーズで働く人材は、0→1で仕組みを作る経験を積めるだけでなく、経営陣と近い距離で意思決定に関わるため、幅広いスキルを得られます。例えば、人事担当であれば採用計画の策定から制度設計まで経験でき、マーケティング担当ならブランド戦略や商品コンセプトづくりに深く関わることができます。こうした経験は、市場価値の高いスキルとして認知され、次の転職時には事業会社のCxOやPEファンド投資先の経営幹部候補として声がかかることも増えます。ゼロから仕組みを作った経験は、どの業界でも汎用性が高い"武器"になるのです。
承継後企業の変革プロセス
プロ経営者が就任してからの半年間は、現状把握と組織の基盤づくりが中心です。人事制度の整備、既存商品の棚卸し、マーケティング戦略の方向性策定といった基礎的な改革が進みます。その後1年程度で、最初の新商品や新施策が市場に投入され、社内に成功体験が生まれます。1年半~2年の間に組織が安定し、ブランドの成長戦略や新規事業への投資など、次のステージに進むための施策が実行されます。このプロセスを間近で経験できるのは、大きな成長機会であり、キャリアの中でも特別な財産となります。
事業承継フェーズだからこそ味わえる面白さ
事業承継後の企業は、変革の余白が大きいフェーズです。ブランドや商品にポテンシャルがあるのに、組織体制が整っていない企業においては、経営者や株主と近い距離で、大きな裁量を持って仕事に取り組むことができます。
PEファンド投資先のようにスピード感を持ってバリューアップを進めるケースもあれば、創業家が外部プロ経営者に舵取りを委ね、少しずつ組織基盤を整えていくケースもあります。いずれにせよ、0→1で仕組みを作り、会社を進化させる経験は、非常に大きなキャリア価値を持ちます。
承継フェーズだからこそできる挑戦
こうした企業で活躍できるのは、
●仕組みのない環境で、自分の手で制度や組織を作りたい人
●マーケティングや商品開発の経験を、経営に近い立場で活かしたい人
●現場と経営の橋渡し役として動ける人
といったタイプです。
承継フェーズで成果を出す経験は、将来的に消費財や小売・外食業界のCxO、あるいはPEファンド投資先での経営幹部として活躍する上で大きな財産になります。
事業承継後の中小企業は、ブランドや商品には力があるのに、組織としての仕組みが未整備なケースが少なくありません。人事・マーケティング・商品開発・経営企画といった機能をゼロから作り上げる経験は、企業を次の成長フェーズに導くだけでなく、候補者にとっても大きなキャリア価値となります。
このフェーズでの挑戦は、単に会社を変えるだけでなく、将来のキャリアを大きく広げるチャンスでもあります。 こうした環境で働く経験は、自身の市場価値を大きく高める貴重な機会でもあります。今後ますます事業承継が進む中、このタイミングだからこそ味わえる"0→1の面白さ"に飛び込む人が増えていくはずです。

執筆者村木 大輔
マネージング ディレクター
●PEファンド投資先の小売業、外食業を中心としたコンシューマー業界のCEO、COO、CMOを中心としたCxOポジションを担当
●日系オーナー企業の小売業、外食業を中心としたコンシューマー業界の部長職から~CxOのマネジメントポジションを担当
Free
Consultation
コンシューマー業界で10年以上の経験を持つ専任のコンサルタントがあなたの転職活動に伴走します。
各社の採用ニーズを熟知し、業界のキーマンともリレーションを持つ専任コンサルタントが転職活動を支援します。
安易に転職は勧めず、戦略的に最適なキャリアを提案します。
転職支援で受けられること
- 専任コンサルタントとの個別面談
- 独占求人(exclusive)の紹介
- 現職の課題分析と将来のキャリア設計
- 年収や待遇の交渉代行
- 業界別の最新動向やトレンド情報
- 入社後のフォローアップ
- 中長期のキャリア支援
- クライアントとの強いリレーション
- 上質で豊富な情報の提供が可能